神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)
〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通1丁目1番4号 のじぎくコーポ2階
受付時間:8:30~18:30(土日祝を除く)
JR神戸駅北口から徒歩3分。近くにパーキング多数あり。
お気軽にお電話ください。
相続、遺産分割、共有不動産問題、事業承継に関する初回法律相談は無料です。お電話でも簡単にご相談頂けます。
まずはお電話下さい。
078-371-0637
遺言書の作成・遺言執行

遺言書で残った財産の分け方を指定しておけば、法定相続人全員の実印印鑑証明書を集めて相続手続きをする必要はありません。
相続人ではない方に遺産を残し、後のことをお願いすることも出来ます。
「まだ、この先何があるかわからないのに、遺言書なんて書けない」と思っておられる方も、大丈夫です。遺言書を書いた後に財産を処分してもいいんです。
この機会に、遺言について、少し勉強しにいらっしゃいませんか?遺言については、お一人でご相談に来られる方も珍しくありません。
「考えてみて、いずれまたご相談します。」と帰って行かれる方が、何年も経ってからお電話を下さり、遺言書を作成なさることもあります。
事前にお電話でお時間をご予約の上、お気軽にお越し下さい。
遺言書を作っておいてよかった事案
法定相続人がいないケース

Aさんには、法定相続人(お子さん、兄弟姉妹、そのお子さんなど)になる方がおらず、いとこの方がいろいろとお世話をしていました。預貯金が2500万円ほどあり、年金もあったのでお金の心配はなかったのですが、Aさんには法定相続人がいないので(いとこは法定相続人ではありません)、Aさんが亡くなると、誰もAさんの預金を下ろすことが出来なくなり、Aさんの預金から病院の支払いをすることも出来なくなります(*1)。
先のことを心配して、いとこの方がAさんを連れて相談に来ました。
Aさんは、このままだといとこの方が安心してAさんのお世話を出来ないことがわかり、遺言書について考えてくれるようになりました。
遺言書があったおかげで、いとこの方は、Aさんの死後、Aさんが入所していた施設の明渡し、病院等の支払い、お葬式などを、Aさんの預金を使って全て滞りなく行うことができました。
(*1)こういう場合には、相続財産管理人の選任申立てをするという方法がありますので、別途ご相談ください)
長年一緒に暮らした内縁の妻に遺産を残したケース

Bさんは、何十年も内縁の奥さんと一緒に暮らしていました。Bさんには、戸籍上の奥さんとその奥さんとの間にお子さんがいますから、遺言書がなければ内縁の奥さんは、Bさんが亡くなると何ももらえないかもしれません。Bさんは随分前に、ちゃんと、内縁の奥さんのこともお子さんたちのことも考えた遺言書を作り、遺言執行者も指定していました。お子さんたちのこともちゃんと考えた遺言書でしたので、あとから遺言の有効性だとか、遺留分だとかで揉めることもありませんでした。遺言書はいつでも書き変えられますが、Bさんが遺言書を書き変えることはありませんでした。途中で財産内容が変わってもいちいち書き変える必要のない遺言書を作っておられました。
遺言書がなくて困った事案
お子さんのいない夫婦

Cさん夫妻にはお子さんがいませんでした。とても仲の良い夫婦でしたが、随分年下の奥さんが突然亡くなりました。奥さんは専業主婦でしたが、Cさんは給料をすべて奥さんに渡し、奥さん名義で貯金をしていました。お子さんがいない場合、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹も法定相続人になりますから、Cさんは、奥さん名義の預金を解約するのに、奥さんの兄弟姉妹全員から実印を押してもらわなければいけません。奥さんの兄弟から「法定相続分はきっちり貰わなければハンコは押せない」と言われ、納得できない気持ちで、奥さん名義の預金の4分の1を奥さんの兄弟姉妹に渡さざるをえませんでした。お子さんのいないご夫婦は、お元気なうちに遺言書を検討しておく必要があります。
若くても遺言書を作っている事案
前妻との間に子供がいるケース
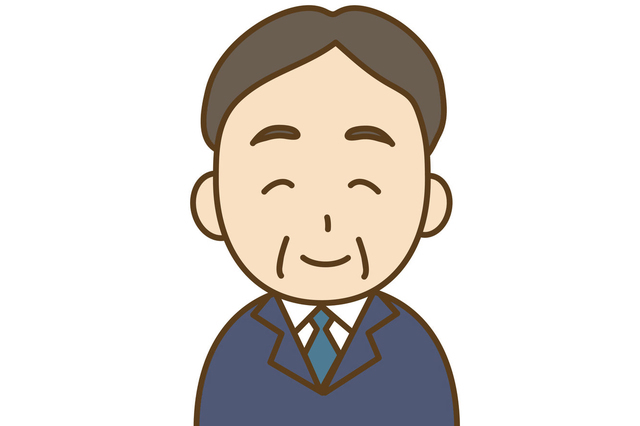
Dさんは再婚で、前妻との間に子供が一人います。今の妻との間にも子供が一人います。
今の家族と前妻の子供とが将来Dさんの遺産のことで話をしなければいけなくなったら、どちらも嫌な思いをするだろうと思い、遺言書を作って遺言執行者を指定してあります。
まずはお電話ください。

お気軽にお電話ください。
タイミングが合えば、お電話で簡単な無料相談を受けていただけることもあります。
時間を予約して、法律相談にお越し下さい。
遺言に関する初回法律相談は無料です。
料金表
基本料金表
| 遺言書作成支援弁護士費用 | ¥15万円(消費税別)~ *財産内容、ご要望事項、ご自宅等への出張の要否などをお伺いして、お見積りさせて頂きます。 |
|---|---|
| 実費(遺産額に応じて公証人に支払う公正証書作成費用、証人の費用が発生します) | |
遺言執行費用 遺言執行者に指定して頂く場合は、遺言執行時に遺産から差し引かせて頂きます。 | 遺言書作成時に遺言者とご相談して遺言執行費用を取決めておきます。 遺言書で遺言執行者に指定して頂いた場合、実際に遺言を執行した際に、遺産から差引かせて頂きます。 |



